
History儀兵衛の「志」
お米の現実を知ってほしい
日本のお米業界は1995年のお米の流通自由化以降、効率化と工業化によってお米本来の味を犠牲にし、縮小の一途をたどってきました。この現状を改善するために会社を立ち上げました、橋本儀兵衛と申します。
目次
まずは、自己紹介をさせてください。
私は、京都で代々続くお米屋の長男として生まれました。大学を卒業し、大手通販会社に勤めた後、家業であるお米屋に戻り、独学でお米の研究をし続けました。その結果、お米がおいしくなる目から鱗のような新しい発見を、いくつも得てきました。お米を研究し続ける日々の中で、私はお米業界が抱える矛盾に悩むこともありました。しかし、それにとらわれていては、せっかく自らの手で発見した本当においしいお米をきちんとお客様にお届けすることはできない。自分は、過去の常識や慣習にとらわれることなく、自由な発想でお客様においしいお米をお届けしたい。そう強く想い、インターネットでお米のおいしさを発信していくことを決めました。おかげさまで、今日まで多くのご反響をいただいております。
皆さん、「神は細部に宿る」という言葉をご存じですか?
本当の仕事とは、目に見えないところにあるという意味で、元々はお米業界も全国にある沢山のお米屋さんが、見えないところでそれぞれの工夫を凝らして皆さんにおいしいお米を届けていました。しかし、1995年お米の自由化という法改正(食糧管理法の廃止)で誰もがお米を販売できるようになったところ、文字で簡単に識別できる、産地・銘柄でしかお米の差別化ができなくなったのです。また、品質へのこだわりを放棄して、安価な代わりにおいしくないお米が世の中に大量に流通したことで、お米本来の味を追求し続けるお米屋さんはたちまち価格で勝負できなくなりました。
私は昔から「物事の本質とは何か?」という考えをもとに仕事に取り組んでおり、農家さんのつくった素材の味をどうすれば100%おいしい状態でお客様にお届けできるのだろうかと考え続けました。そして、産地・銘柄だけにこだわらず、まだ見えていないものを手探りで1つずつ確かめていきました。結果、おいしいお米に不可欠な4つのこだわりにたどりついたのです。それは、ただ一意専心においしいお米を追求し続けることでしか得られないものでした。京セラ株式会社の故・稲盛名誉会長の言葉を借りるなら「叡知の蔵を開く」とでも言いましょうか。そんな目には見えない本質を探る仕事を、八代目儀兵衛は創業以来ずっと続けてきております。
八代目儀兵衛のお米は、赤ちゃんにも無意識においしいと感じてもらえるお米のみを販売しております。
赤ちゃんは感覚でごはんを食べています。おいしいと感じるものは無意識においしく食べていますし、おいしくないもの、身体に合わないものは食べようとしません。そんな赤ちゃんの姿を見たことはありませんか? 赤ちゃんは銘柄や産地を知りません。本質を感覚でつかみ取って、食べるものを選んでいるのではないかと思います。
赤ちゃんがすすんで食べるような本当においしいお米を、日本のみならず、世界中の人たちにも広めていきたいと考えております。是非、皆さんも儀兵衛でお米の感動体験をしていただき、お米の本来のおいしさとは何かを考えていただけると幸いです。
さて、ここからはお米業界の現状についてクローズアップしてお話ししたいと思います。
お米は「日本の主食である」と言われ続けてきました。しかし、個食化が進むことでお米を炊く手間を煩わしく感じたり、食の欧米化が進みパンや麺類といった代替品が使用されたりと、必ずしもお米を主食としない生活が我々にとって当たり前の世の中になってきたと思います。最近ではお米の糖質の高さがクローズアップされ、敬遠されがちな食材になってしまいました。
かくいう私自身もパンや麺類を食べないわけではありません。どちらかと言えば好きな方だとさえ思います。ですが、一日一食はおいしいごはんを必ず食べております。
最近のお米の消費量の調査では年々消費量が少なくなっており、50年前に比べると半分以下になっているそうです。
ここまでは消費者の話をしてきました。では、生産現場はどうでしょうか?
お米の生産地の過疎化や生産者さんの高齢化、地球規模の温暖化によって昔とは環境も大きく変わり、真夏には気温が40度近くにまで上昇するなど、お米品質を向上させていくには本当に厳しい状況にあります。そして、それ以上に日本人のお米離れ(お米への関心の薄れ)が顕著になり、もはや産地で新しい品種開発をしても、その違いを気にすることやそこに興味を持つ人が少なくなってきています。私個人としても、相対的に昔と比べて本当においしいお米の生産量が少なくなったなと実感しております。これからは食糧難の観点から、生産者さんの手間を省きつつ、さらに大量に生産できることを重視したお米へと世の中がシフトしていくでしょう。食味よりも収量を優先する、そんな時代になっているのです。
そんな現実に置かれる中で、儀兵衛として皆さんに特に知ってもらいたい事実が5つあります。

子供たちはごはんに味がないと認識しているから
食べないという事実
私が、20年前お米マイスターとして小学校の食育授業を担当した時のことでした。
まず、今朝、朝食を食べてきた人に手を挙げてもらったところ、結果は半数ほど。そして、ごはんを食べてきた人数を確認すると、さらに半分以下。やはりごはんは手間がかかるものとして、若い夫婦には敬遠されがちなのだと感じました。
しかし、それよりも衝撃だったのは「どうしてごはんを食べないの?」という質問への子供たちの答えです。「白ごはんには味がない」「コンビニおにぎりの方が味がしておいしい」「ふりかけをかけないと食べられない」といった言葉がありました。そもそもごはんの素材の味を全く理解していなかったのです。私がお米屋で育ってきたためでしょうか。まさかそんな風に認識されているとはついぞ考えておらず、非常に残念な想いをして帰ってきました。
たまたま京都の小学校で経験したことではありましたが、全国にも同じように感じている子供たちは沢山いるんだろうと思います。彼らが大人になった時には、お米を食べるという選択肢がすでに無くなっていると考えることも大げさではないでしょう。
ただ、子供たちの言葉に、思い当たる節があります。
後でまた詳しく言及しますが、精米はすればするほど、お米の見た目は白くなります。ただ、その一方でおいしさは損なわれていきます。しかし、消費者の中には、白くなければ不良品だと思っている方もいらっしゃるようです。そこはお米のプロとして「お米のおいしさは見た目の白さとイコールではない」ということを知っていただくような施策を、本来するべきです。
しかし残念ながら、クレームが来ることを恐れて、必要以上に白く精米するお米販売店が多くあります。そして、スーパーや量販店ではそのように精米された激安のお米ばかりが購入されていきます。こうして、日常的に食べるお米に「味がない」と感じる子供も増えているのでしょう。
おいしいお米を選ぶという選択肢が抜け落ちているだけではなく、お米のおいしさそのものが分からなくなっている、そんな現実があると思っています。

お米が産地・銘柄でしか評価されていないという事実
皆さんがお米を買う際に、産地を気にすることもあると思います。また、お米に関してはこしひかりが一番おいしい品種だと強く思っている人もいらっしゃると思います。それが悪いわけではありません。しかし、真実を言えば、産地・銘柄の情報だけでおいしさを計ることはできないのです。私はお米屋なので、知人やメディアから「おいしいお米の産地を教えて!」とよく聞かれます。産地ごとに、大きくタイプ別に特徴を仕分けすることはできますが、全てのお米がそれに当てはまるものでもありません。厳密にいえば、隣同士の田んぼですらお米の味は異なるものです。また、土壌環境だけではなく、使っている肥料や生産者さんの考え方もお米の味わいにかなり影響します。お米の味は、単純に産地でくくれるほど簡単な要素で成り立っていないのです。
そして、お米の買取価格は都道府県ごとに値段が変わるため、有名産地であれば高く買取してもらえますが、無名産地は努力しておいしいお米をつくっても、評価されずに安く買取されるという現実もあります。現状のお米の評価は食べておいしいお米より、産地や見た目による等級検査だけで評価されているところに、日本の米農業の深い問題があると言えます。
お米は一粒一粒に産地や品種名が書いてあるわけではないので、皆さんは自分が知っている知識の中で選ぶしかありませんし、店舗に出かけても有名産地のお米と地元のお米しか売ってないため、その中でしか選ぶことができません。事実、インターネットで検索すると有名ブランドのお米か、価格の一番安いお米しか上位に出てこないので、選択肢が本当に限られてしまっています。どのお米が自分にとって最適なのかわからない、それが今の日本におけるお米の事実です。

精米によって味や食感が変わる重要性が
知られていないという事実
皆さんはお米の精米について深く考えたことはありますか?
皮のついた玄米を摩擦して剥(む)くことを精米と言います。ここまでは皆さんご存じでしょう。ただ、精米機メーカーによって機械のサイズが大小様々あり、剥き方によって味や食感が大きく異なることはご存じでしょうか?
精米したてのお米はなんだか温かくて、それにより剥きたて感や鮮度が保たれ、おいしくなりそうなイメージがあります。私もずっとそう思ってきましたし、事実、精米から日が新しければ新しいほどおいしいごはんに炊きあがります。ですが、実際はそれだけではありませんでした。大きな盲点として存在していたのは、剥き方だったのです。
お米屋で仕事をしていたある時に、得意先様から「いつものお米と味が違う。混ぜもんしたんと違うか?」とお叱りをいただいたことがありました。しかし、私たちはそのお得意様にはいつもと同じ産地、生産者に限定していたものをお届けしていました。なぜこのようなことになったのだろう、と考えた時に、ある違いに気付いたのです。このときだけは、いつもとは違う精米機で精米したものを納品していました。
その当時、メーカー違いとサイズ違いの精米機が3台あり、早速その3台で同じ産地、生産者さんのお米を精米してみました。すると、全く違うお米の味・食感になったのです。そこから深く研究した結果、よりおいしいお米に仕上げるためには、温度をいかに低く抑えて精米するかが重要だという、驚愕の事実を発見しました。これによって、お米業界の問題がまた1つ浮かび上がりました。世の中の味のしないお米のほとんどは、精米によって素材本来の味を削ってしまっているのです。
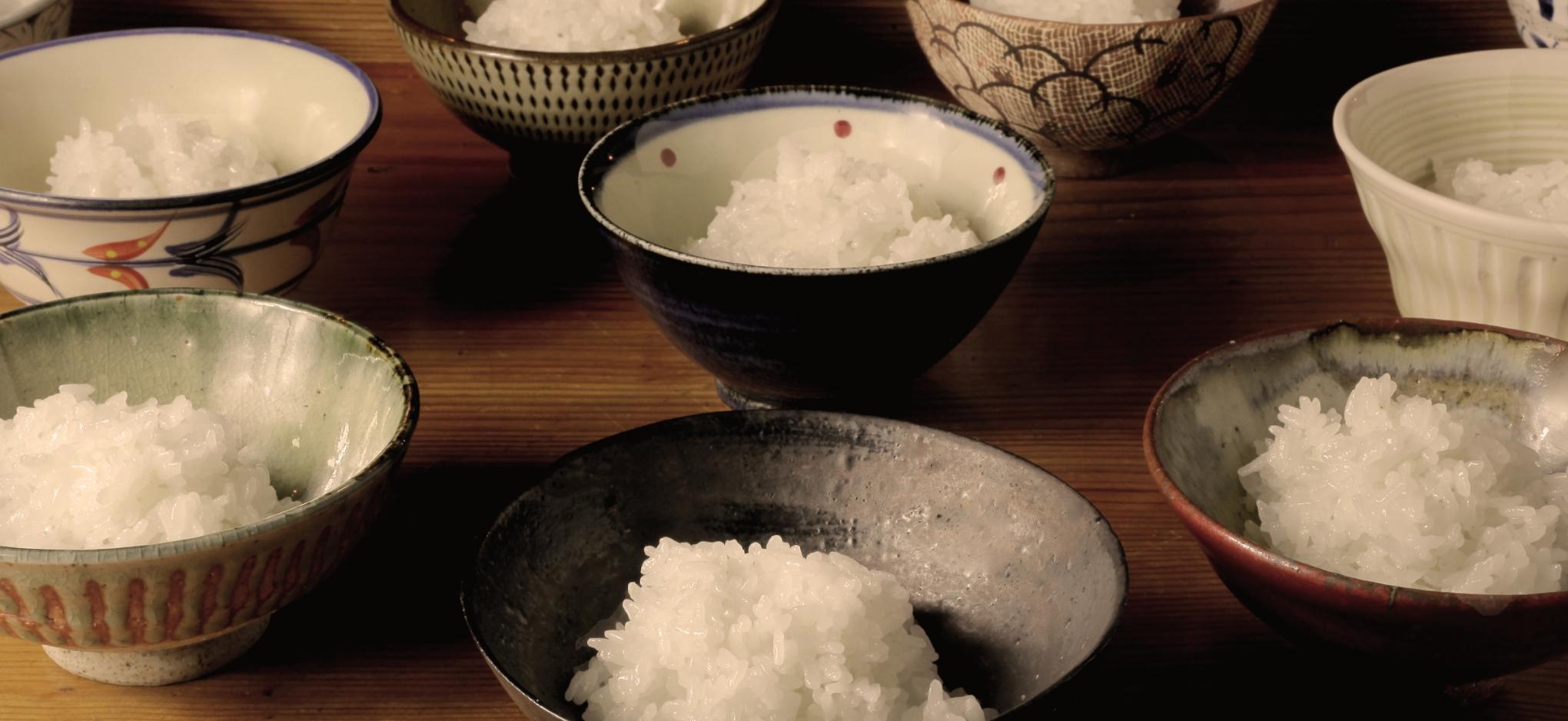
本当はブレンドしたほうがお米の甘みは増す
という事実
食品業界には、素材の味を組み合わせてより立体的で深みのある味に仕上げるブレンド技術が当たり前に存在します。和食に代表されるお出汁は、昆布とかつおの削り節によってさらに深みのある味になります。皆さんが普段から飲むコーヒーもブレンドすることで、味のバランスを整えたり、特徴を出すことでその店の個性を打ち出すことができます。
一方でお米においては、ブレンドすることでまがい物扱いされるなど、おいしいという評価を得ることがほとんどありませんでした。確かに、お米はシングルオリジンの味を楽しむ人が多いのも事実です。ただ、お米という繊細な味わいを有する食品は、ブレンドすることでこそ、より深い味を生み出すことができます。お米の味わいが、そして楽しみ方が広がるのです。独自のブレンド技術でその広がりを表現することがお米屋の個性を出すことでもあり、斜陽産業でもあるこのお米業界の唯一の生き残り方法でもありました。
儀兵衛では、甘みが強いお米こそがおいしいお米と考え、甘みと粒立ちに特化したいくつもの独自のブレンド技術を有しています。それが評価され、現在では900以上の取引先にお米を卸しています。
中でも、ミシュラン3つ星の祇園さ々木さんとは先代からお付き合いがあり、強く影響を受けています。私が考案したブレンド米を何十回も試食していただき、試行錯誤の上、ご満足いただけるレベルの商品が完成しました。さ々木さんはいつも「旨いは甘いんや!」と仰っており、その言葉は私の記憶にも深く刻み込まれています。その言葉を基に、年間ブレンド試食会数は2,000回以上実施しております。お米はブレンドした方が甘みが増すという事実は、さ々木さんのお店で使っていただいたことで証明できたと言っても過言ではありません。

「お米のおいしい炊き方」が知られていないという事実
皆さん、お米はどのようにして炊いていらっしゃいますか? ご両親から教えていただいたやり方や、料理本に書いてあるものを実践しているなど、さまざまなお考えでお米を研いだり炊いたりされていらっしゃるかと思います。
私も過去に料理本を見たことがありますが、一合も本によっては140gだと言い切るところもあったり、計量カップ一杯が適量だという本もあったりと、情報はさまざまです。お米の研ぎ方ひとつとっても、最近は精米機の性能が上がっているから研がずにかき混ぜるだけでいいとか、研ぐのは3回以上とか、バラバラのことが書かれています。何が最もおいしい炊き方であるかは、料理本の中でさえ共通の認識はなさそうです。
中には目を疑うような記述がある場合もあります。早く炊飯するためにお米を金ザルで研いだり、水を切った状態で放置していたり、お米のプロである私から見たら間違いだらけの炊飯方法が書かれているのです。そうした間違った炊き方をした結果、おいしくなかったらお米屋のせいにされることも多々あります。
お米のおいしい炊き方が知られていないのは、何も家庭に限ったことではありません。外食をした時にも、本当においしいと思えるごはんを提供してくれるお店はほんの一握りです。どれだけいい素材を使っていても、おいしくする研ぎ方・炊き方を知らなければ、全く意味がありません。我々お米屋は、その事実を知っているので、お米の味を引き出すおいしい炊き方をいつもお伝えしています。勉強になったと仰ってくださる方もいらっしゃる一方、中には見向きもしてくれない料理人さんもいました。そんな現実もあるということを、知っておいていただければと思います。
以上のお米業界の現実を何とかして解決し、本当においしいお米、そしてそのお米を使って炊いたおいしいごはんを八代目儀兵衛が、日本中の人達、日本のお米を愛してくれている世界中の人達に届けたい。それが実現できれば、日本人のお米離れもなくなり、多くの人がお米に再び関心を持つことでしょう。そうなった暁には、世界中の人達から、日本のおいしいお米が求められるようになるのではないかと考えています。日本のお米にはそれだけの力があると信じているのです。
そこで、八代目儀兵衛は4つのこだわりをソリューションとして、皆様にお米本来のおいしさを伝えてまいります。
2023年9月 橋本儀兵衛

 事業紹介
事業紹介








